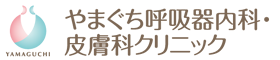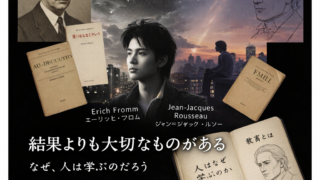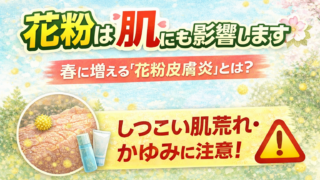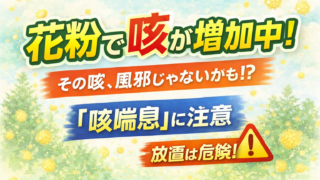2024年 寒暖差アレルギーについて

寒暖差アレルギーについて
秋になると気温の変化が激しく、朝晩と日中の温度差が大きくなることがあります。
このような気温の変化により、「寒暖差アレルギー」と呼ばれる状態が生じることがあります。
今回は、寒暖差アレルギーの症状や原因、そしてその対策について詳しくお伝えします。
寒暖差アレルギーとは?
寒暖差アレルギーは、実際にはアレルギーではなく、気温の急激な変化に対して自律神経が過敏に反応することで起こる状態です。
自律神経は体温調節を行っており、急な温度差が生じるとそのバランスが乱れ、さまざまな不快な症状を引き起こします。
寒暖差アレルギーの主な症状には以下のようなものがあります:
- 鼻水や鼻づまり: 温度差により鼻の粘膜が過敏になり、アレルギーのように鼻水や鼻づまりが生じます。
- くしゃみ: 鼻の敏感な状態が続くと、くしゃみが頻繁に出ることがあります。
- 肌荒れやじんましん: 皮膚がかゆくなったり、赤みが出たり、じんましんのような症状が現れることがあります。
- 頭痛や倦怠感: 自律神経の乱れにより、体がだるく感じたり、頭痛が生じることがあります。
寒暖差アレルギーの原因
寒暖差アレルギーの原因は、気温差による自律神経の乱れです。
自律神経は、体温や血流の調整を行い、環境に適応しようと働きますが、急激な温度変化があるとその調整がうまくいかず、様々な症状が引き起こされます。
特に、以下のような気温差がある状況で発症しやすくなります:
- 外気と室内の温度差: 秋や冬には、外が寒い中で暖房の効いた室内に入ると、温度差が大きくなり自律神経が過剰に反応することがあります。
- 季節の変わり目: 朝晩と日中の気温差が大きい時期に、寒暖差アレルギーの症状が現れやすくなります。
寒暖差アレルギーの対策
寒暖差アレルギーを防ぐためには、以下の対策を心掛けてください:
- 温度差を少なくする工夫: 外出時には、薄手のジャケットやストールを持参し、外の寒さと室内の暖かさの間で温度調整ができるようにしましょう。また、室内の温度を急激に上げすぎないようにし、できるだけ自然な形で温度を調節することも大切です。
- 規則正しい生活リズムを保つ: 自律神経のバランスを整えるために、規則正しい生活リズムを保つことが重要です。十分な睡眠をとり、栄養バランスのとれた食事、適度な運動を心掛けましょう。
- 体を冷やさない工夫: 冷えは自律神経の乱れを悪化させます。外出時にしっかりと防寒対策をし、冷えやすい首元や足元を温めるようにしましょう。温かい飲み物を飲むことも効果的です。
- ストレス管理: ストレスも自律神経に悪影響を与える要因の一つです。趣味やリラックスできる時間を取り入れて、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
まとめ
寒暖差アレルギーは、急激な温度変化により自律神経が乱れることで引き起こされる症状です。
鼻水やくしゃみ、肌荒れなどの不快な症状が現れますが、規則正しい生活リズムや温度差を少なくする工夫で予防することができます。
もし寒暖差アレルギーの症状が長引いたり、日常生活に支障が出るようであれば、医師に相談することをおすすめします。
当院では、寒暖差アレルギーに関するご相談を随時受け付けております。
症状が疑われる場合は、ぜひご相談ください。
投稿者プロフィール
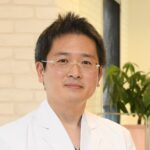
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞