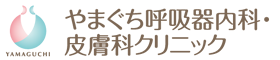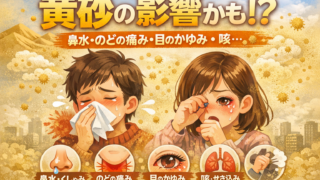脳血管障害・脳卒中と咳は関連しますか?

脳血管障害・脳卒中と咳は関連しますか?
やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニックの山口裕礼です。
脳血管障害や脳卒中と咳の関係について解説します。
脳の機能障害が呼吸や咳に与える影響や注意すべき症状について説明します。
1. 脳血管障害・脳卒中が咳に影響を与える理由
脳血管障害や脳卒中(脳梗塞や脳出血など)は、脳の機能障害を引き起こし、その結果、呼吸や咳に影響を及ぼすことがあります。
特に、脳の呼吸中枢や気道反射を制御する部分が損傷を受けた場合、咳の反射や呼吸機能が変化する可能性があります。
2. 脳血管障害後に起こり得る咳の原因
脳血管障害や脳卒中が原因となる咳の具体的な要因には以下のものがあります:
- 嚥下障害:脳卒中後の嚥下機能の低下により、食べ物や飲み物が気道に入る「誤嚥」が起こりやすくなり、咳が反射的に生じます。
- 気道の分泌物増加:呼吸機能の低下や体位変換が少ない場合、痰が気道に溜まりやすくなり、咳を誘発します。
- 呼吸筋の弱化:脳卒中による麻痺や筋力低下が呼吸筋にも影響を与え、咳をする力が弱くなることがあります。
- 誤嚥性肺炎:嚥下障害や誤嚥が続くと、肺炎が引き起こされ、咳や発熱、息切れを伴うことがあります。
3. 注意すべき症状
脳血管障害後の咳に関連して、以下の症状が見られる場合は注意が必要です:
- 食事中や飲水中にむせることが多い
- 痰や咳が長引き、発熱や倦怠感がある
- 呼吸が浅く、息切れを感じる
- 痰が黄色や緑色に変わる(感染症の兆候)
これらの症状がある場合、早急な医療機関での診察が必要です。
4. 咳の改善に向けたアプローチ
脳血管障害後の咳や呼吸機能を改善するためには、以下のような対応が有効です:
- 嚥下リハビリテーション:専門家による嚥下訓練が、誤嚥を防ぎ咳の軽減に役立ちます。
- 体位管理:ベッドでの適切な姿勢や体位変換が、痰の排出を促進します。
- 吸引や吸入療法:痰が多い場合は吸引や吸入療法を利用し、気道を清潔に保ちます。
- 肺炎予防:定期的な口腔ケアや予防的なワクチン接種(インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン)が推奨されます。
5. 医師に相談すべきタイミング
以下のような場合には、速やかに医師に相談してください:
- 咳とともに発熱や倦怠感がある
- 食事中にむせる頻度が高くなる
- 呼吸困難や血痰が見られる
- 胸痛や意識低下を伴う
最後に
脳血管障害や脳卒中後の咳は、適切な診断と治療、リハビリテーションによって多くの場合改善が期待できます。
当クリニックでは、呼吸機能の評価と治療を行い、患者さん一人ひとりに合ったサポートを提供しています。
気になる症状がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニック 山口裕礼
投稿者プロフィール
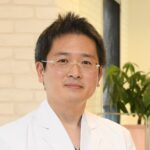
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞