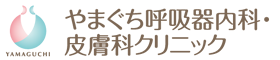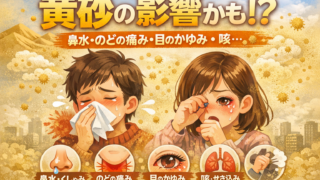もっと知ろう!「ロコモティブシンドローム」

健康で自立した生活のために
皆さん、こんにちは。今日は「ロコモティブシンドローム」(略して「ロコモ」)について、その重要性と予防策に焦点を当てて話を進めたいと思います。
ロコモティブシンドロームとは
ロコモティブシンドロームとは、加齢や病気により筋力が低下したり、関節や脊椎、骨粗しょう症など運動器の疾患が原因で、身体の動きが制限され、結果的に要介護や寝たきりになるリスクが高まる状態を指します。
この言葉は、日本整形外科学会によって提唱され、高齢化が進む現代日本において非常に重要な概念となっています。
長寿国日本とロコモ
日本は世界でも類を見ない長寿国で、平均寿命は男性79.9歳、女性86.4歳にも達しています。
しかし、長寿であることは必ずしも健康で自立した生活を意味するわけではありません。
事実、要介護認定者数は年々増加し、特に75歳以上の約3人に1人が要介護状態にあるとされています。
ロコモの原因と予防
ロコモを引き起こす主な原因の一つが運動器の障害です。
特に、変形性膝関節症、変形性腰椎症、骨粗しょう症が主な疾患として挙げられます。
これらの疾患は、日本人の腰痛や下肢の痛みの原因ともなっており、放置することでさらなる運動器機能の低下を招きます。
健康な生活のためのロコモ予防
ロコモ予防のためには、定期的な運動が非常に重要です。
スクワットや片足立ち、ウォーキングや水中歩行など、さまざまな運動を習慣にすることで、運動器の病気の予防や機能低下の改善につながります。
また、骨粗しょう症に対しても、背筋訓練や踵上げといった運動が骨強度の改善に役立ちます。
ロコモティブシンドロームの予防は、ただ運動をするだけでなく、日常生活の中で意識的に身体を動かすこと、適切な栄養摂取や定期的な健康チェックも含まれます。
特に女性は、骨粗しょう症によるリスクが高いため、積極的な予防が求められます。
まとめ
ロコモティブシンドロームは、私たちが長寿を全うする上で避けて通れない課題です。
しかし、早期からの予防策を講じることで、健康で自立した生活を長く続けることが可能です。
日常生活における小さな工夫や運動の積み重ねが、大きな未来への一歩となります。
私たちの手で、健康な「人生100年時代」を切り拓きましょう。
投稿者プロフィール
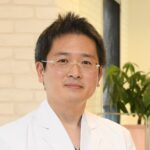
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞