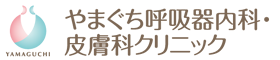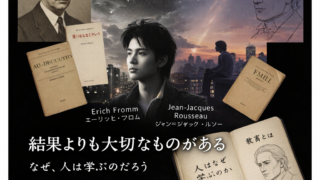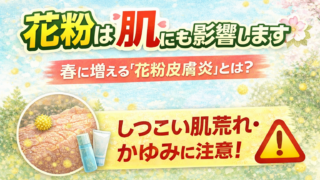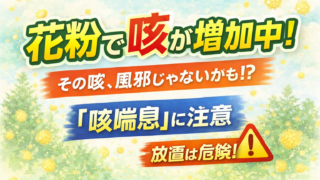薬を嫌う患者さんへ:治療に対する選択肢とその影響について

薬を嫌う患者さんへ:治療に対する選択肢とその影響について
医療の現場では、薬を極力使いたくないと考える患者さんが少なくありません。
これは治療に対する考え方や価値観が一人ひとり異なるためです。
この記事では、薬を避けながらも医療機関に頼る場合の治療経過や結果について、いくつかのパターンをご紹介します。
1. 薬を最小限に抑えつつ、医師との連携を維持する場合
薬をできるだけ避けたいという場合でも、医師としっかりと話し合い、生活習慣の改善や食事療法、運動など薬以外の方法を取り入れることが可能です。
このアプローチでは、症状のコントロールが難しい場合もありますが、定期的な診察や検査を通じて進行具合を確認し、必要に応じて薬の使用を再検討することで、病気の悪化を防ぐことができます。
患者さんが積極的に健康管理を行い、医師と密にコミュニケーションを取ることで、症状の改善も期待できます。
2. 薬を避け、医療機関との接触も減らす場合
薬物療法を避けるだけでなく、医療機関への受診頻度も減らすと、自己判断による治療放棄に近い状態になります。
特に慢性疾患の場合、症状のコントロールが難しくなり、病気が進行してしまうリスクがあります。
例えば、喘息や糖尿病、高血圧といった病気では、薬物療法を中止することで病状が悪化し、最悪の場合は緊急入院や合併症のリスクが高まります。
3. 薬の使用を拒否した結果、症状が重症化する場合
薬を嫌い、治療を遅らせることで病気が進行してしまうこともあります。
特に感染症や炎症性疾患では、早期治療が効果的ですが、治療を避けることで症状が悪化し、結果的に強力な薬や長期間の治療が必要になることがあります。
この場合、患者さんが最初に避けたかった薬の使用が避けられなくなることもあり、治療が複雑化する可能性があります。
4. 患者さんの選択を尊重しつつ、リスクを伝える
最終的には、医療者として患者さんの意思を尊重しながらも、病気の進行を抑えるために最低限必要な治療があることを説明する必要があります。
「今後症状が悪化すると、選択肢が狭まる可能性がある」というリスクを正直にお伝えし、薬以外の方法では限界があることを説明することが重要です。
まとめ
薬を嫌う患者さんにとって、治療の選択は難しいものです。しかし、医師としては、治療の利点とリスクを丁寧に説明し、患者さんの健康状態に最適な選択を一緒に考えることが大切です。
患者さんが自分の健康について理解を深め、信頼関係の中で治療に取り組むことで、最良の結果を得られる可能性が高まります。
信頼できる医療チームとともに、健康を維持するための最善策を探っていきましょう。
投稿者プロフィール
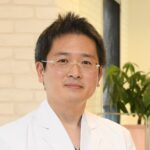
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞