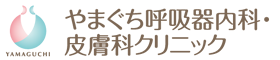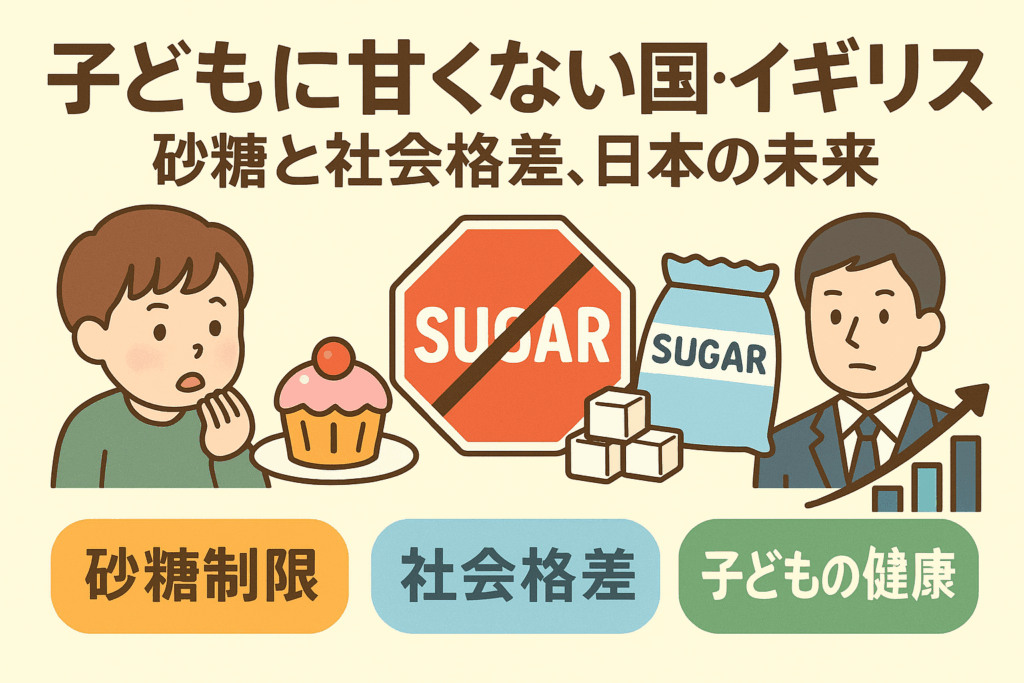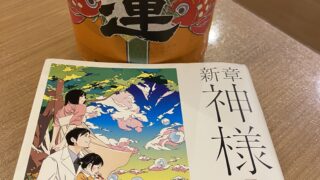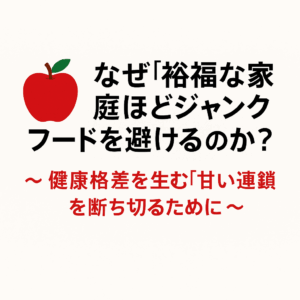🍬子どもの食は「親の努力」だけでは語れない

〜どれだけ気をつけても、人生は本人のもの〜
先日のブログでは
“砂糖・ジャンクフードと社会格差”
そして
“スコットランドの取り組み”
について触れました。
今日は、
実際にお聞きした 2人のお母さんのエピソード を通して
「子どもの食」と「親の役割」について
さらに深く考えてみたいと思います。
🟡 ケース①
100年以上続くぬか漬けの家系
正しく育てても、子は子の人生へ
あるお母さんが話してくれました。
「我が家は代々100年以上、ぬか漬けを続けてきました。
子どもには自然なもの、体に良いものを食べさせてきました。
ジュースやお菓子は極力控えてきました。」
家庭での食育は徹底。
食材にも気を配り、料理にも手間を惜しまない。
母としてできることをすべてやってきたそうです。
けれど子どもは成長し、
友人関係も広がり、
知恵もつき、
やがて
自分の好きなものを自由に選ぶようになります。
「子どもは好き勝手にお菓子を食べるようになり、
気づけば病気になっていました。」
――どれだけ親が努力しても、
子どもの人生は“子ども自身のもの”
であるという厳しい現実。
このお母さんは
深い悲しみとともに
それでも
「私はやれることはやった」と
静かに語っていました。
🟢 ケース②
幼少期は砂糖ゼロ
誕生日会が人生の転機に
別のお母さんは、
幼少期、お菓子を一切与えなかったそうです。
「砂糖は悪い。
子どもには本物の味を覚えてほしかった。」
家では甘いものを出さず、
徹底した“自然派の子育て”。
しかしある日、
子どもが友達の誕生日会に招かれ
初めて“お菓子”に出会います。
ケーキ、チョコ、ジュース……
甘い味の刺激に
子どもは一気に飲み込まれてしまった。
「その日からお菓子にハマり、
止まらなくなってしまいました。」
こちらも
親としての努力が
必ずしも望む結果につながらない現実を
物語っています。
🍭「正解のない世界」
親は“ベストを尽くすしかない”
この2つの例は
正反対のアプローチなのに
どちらも難しい結果に至っています。
✅ 徹底して良いものを与えても
→ 子どもは成長し選択を変える
✅ お菓子を避けても
→ 外の世界で出会えば魅了される
どこに答えがあるのでしょう?
実は
子どもの食育には
絶対の正解はありません。
親は
できる限りの教育・環境・愛情を与える。
そのうえで
最終的に人生を選ぶのは
子ども本人 です。
🌱だからこそ
「完璧でなくていい」
大切なのは
✅ 与える食の質
✅ 選ぶ力
✅ ほどよく楽しむ
✅ 依存を避ける
など
“食とのほどよい距離感” を
子どもが身につけること。
親ができるのは
そのサポートです。
完璧を目指す必要はありません。
できることを、できる範囲で。
🧠 最後に
子どもの人生は、子どものもの
親は
子どもの幸せを願います。
健康であってほしいと願います。
しかし
人生は
親の所有物ではなく
子どものもの。
食習慣も、
健康も、
選択も、
最終的には
子ども自身が引き受けていく。
親にできることは
ただ
「最善を尽くす」
ということだけ。
そして
それで十分です。
🍀
本ブログが
「食育」と「子育て」の
本質を考えるきっかけになれば幸いです。
投稿者プロフィール
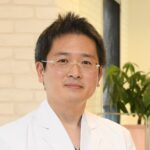
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞