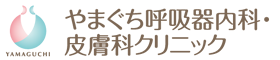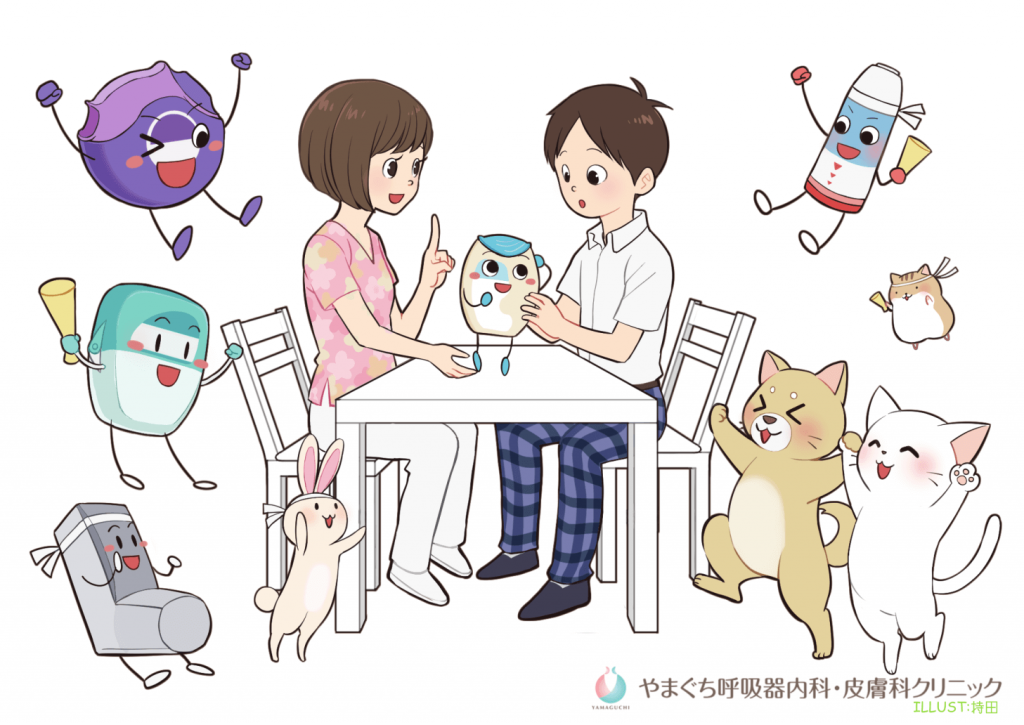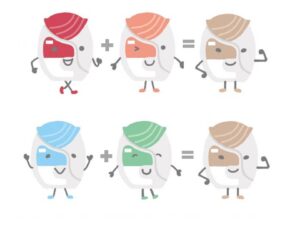💊初回からのテリルジー処方、薬剤師としてどう向き合うか

🩺現場で求められる“ひと声”のチカラ
はじめに🔍
「初診でテリルジーが処方された…」
最近、そんな処方せんを目にすることが増えていませんか?
吸入薬の進化により、便利で強力な3剤配合薬が登場しましたが、
“初回からのテリルジー処方”にはリスクも潜んでいます。
今回は、薬剤師として知っておきたい
💡テリルジーの正しい位置づけと、
💬患者さんや医師との橋渡し役としての“気づき”を整理します。
1️⃣ テリルジーは「治療ステップアップ後」の薬💨
📖喘息治療の最新ガイドラインでは、
症状の程度や反応に応じて段階的に薬剤を調整する「ステップ治療」が基本です。
👉 テリルジーは 「中等症以上で、コントロール不良」な場合の上位選択肢。
初診・初回での処方は、基本的に想定されていません。
そのため、薬局で以下のような確認が必要になるケースがあります:
🔸 他の吸入歴はあるか?
🔸 診断は喘息か?咳喘息か?COPDとの鑑別は?
🔸 デバイスの操作は問題なさそうか?
2️⃣ 薬剤師が注意すべきポイント🧠
💥副作用と薬効の“誤差”に注意!
テリルジーには以下の副作用リスクがあります:
- 口腔カンジダ(ステロイド)
- 排尿困難・口渇(LAMA)
- 声枯れ・動悸・振戦(β2刺激薬)
患者が「飲み薬ではないから大丈夫」と思いがちな吸入薬だからこそ、
副作用の丁寧な説明が必要です。
🌀吸入ミスは“ゼロ効果”
特に初めて吸入する患者さんでは、
デバイス操作のミスによって、薬が肺まで届いていないことがしばしばあります。
🔹 Elliptaは簡便と言われますが、
→ 「息を止める時間が短い」
→ 「吸気が弱い」
など、見落とされやすいエラーも存在します。
📣 薬局での吸入指導は、処方医の方針と連動させながら、
“伝えるべきこと”を絞って丁寧に伝えることが重要です。
3️⃣ 医師との連携で活きる「気づき」✍️
テリルジーが初回処方されている背景には、
✅ 医師が喘息専門でないケース
✅ 患者が強めの薬を希望した場合
…などが考えられます。
💬 薬剤師として、医師に以下のようなフィードバックができるとベストです:
- 「以前は吸入歴がなく、今回が初めてのようです」
- 「デバイス習得に不安がありました」
- 「咳が主訴で、喘鳴や気流制限の話は出ていない様子です」
この“ひと声”が、患者の未来を変えることもあるのです🌱
✨まとめ
🔸 テリルジーは便利な薬ですが、“最初の一歩”としては強すぎることも。
🔸 薬剤師は、吸入チェック+背景把握+副作用指導という3つの視点が重要です。
🔸 時には医師へやんわりと「確認のきっかけ」を投げかけることも◎
💬薬剤師のひとことが、患者の未来をつくる🌈
吸入薬は「技術介入」が大きい治療法。
薬剤師の専門性が活きる場面がたくさんあります。
テリルジーが適正に使われ、
患者さんが安心して治療を続けられるように。
“気づく力”と“つなぐ力”が、いま求められています💎
投稿者プロフィール
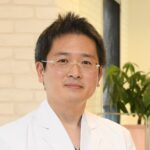
-
からだ整えラボ
① 医学=呼吸器・アレルギー
② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌
③ 幸福=働き方・環境・園芸
“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”
——その思いを胸に、学びを続けています。
医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ
三位一体の医療をめざしています。
資格:
<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート
<予防医学・代替医療・環境>
機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨
カラダ取説®マスター・ジェネラル
環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター
<文化・生活>
日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)
<受賞歴>
第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞
最新の投稿
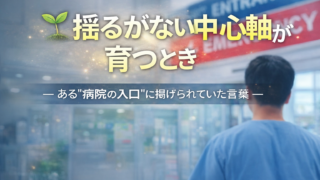 からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき
からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき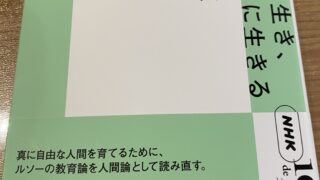 クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊
クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊 からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥
からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥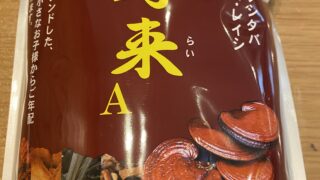 からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊
からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊